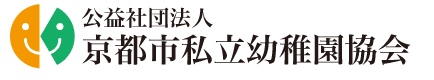【新連載】幼児期の子どもへの関わりにおいて 大切なこと3 ~子どもの言動には必ず背景と理由がある~ 4 回シリーズ(3)
京都府・京都市スクールカウンセラー臨床心理士 大下 勝
スクールカウンセラーとして学校現場で勤務していますと、先生方から子どもの問題行動に関する相談を受けることがあります。例えば、授業中立ち歩く、よくトラブルを起こして暴力をふるう、自分の良くなかった行動を認めず絶対謝らないなどです。子どもの成長過程では経験不足によって問題行動が起こることはよくありますが、何回注意しても変化がない場合は、子ども自身もうまくコントロールできずに困っていることが多いです。同じことを何度も繰り返しますので、感情的な対応になってしまうこともあるかと思います。
そして、子ども自身を否定するような関わりを多くしてしまうと問題行動がさらに悪化することがあります。本当は本人自身が困っているのに、繰り返し否定され続けると、「自分はダメな人間だ、どうせがんばってもできない」と思うようになり、自尊心や自己効力感が低下していきます。この状態になると回復するのにかなり時間がかかることが多いので、問題行動が多い子どもには慎重に対応する必要があります。
では、どうしてこのようなことが起こるのでしょうか。人にはそれぞれ生まれ持った個性があり、様々な性格特性があります。その特性が日常生活を問題無くおくれるものであればいいですが、偏りが大きい場合は本人も周りの人も大きな困りを抱えることがあります。特に幼稚園から小学校にかけては、ルールが増えてきて、性格特性が原因で適応できなくなる子どもが出てきます。困りがあまりにも大きい場合は、医師により診断がおりることもあります。ここで特に注意したいことは、診断は本人にレッテルをはるものではなく、本人を理解する助けになるものでなければなりません。言い換えると、診断がでるほど本人は困っているので、周りがしっかり配慮する必要があるということです。さらに、育った環境によっては、愛着課題を持つ子どももいます。生まれ持った性格特性とは違うのですが、同じような問題行動を起こします。ただ、性格特性が原因の場合は本人にあった環境に調整することで、ある程度落ち着くと言われていますが、愛着課題の場合は、違う問題行動に変化したり、大人を振りまわすようなお試し行動が起こったります。これら性格特性と愛着課題に関してはかなり専門的な内容になりますので、可能ならキンダーカウンセラーなどの専門家に相談されることをお勧めします。
幼稚園の先生方におかれましては、すでに専門書や研修等で幼児期の子どもの理解や対応について幅広く学ばれていることと思いますが、実際にはなかなか難しいケースも多いのではないでしょうか。そういったときに今一度、「子どもの言動には必ず背景があり、理由がある、子ども自身が困っている」ことを再確認していただけますと、(前回の会報でお伝えしたように)子どもの言動は注意したとしても、子ども自身がしっかり受けとめられたと感じる関わりができるのではないかと思います。